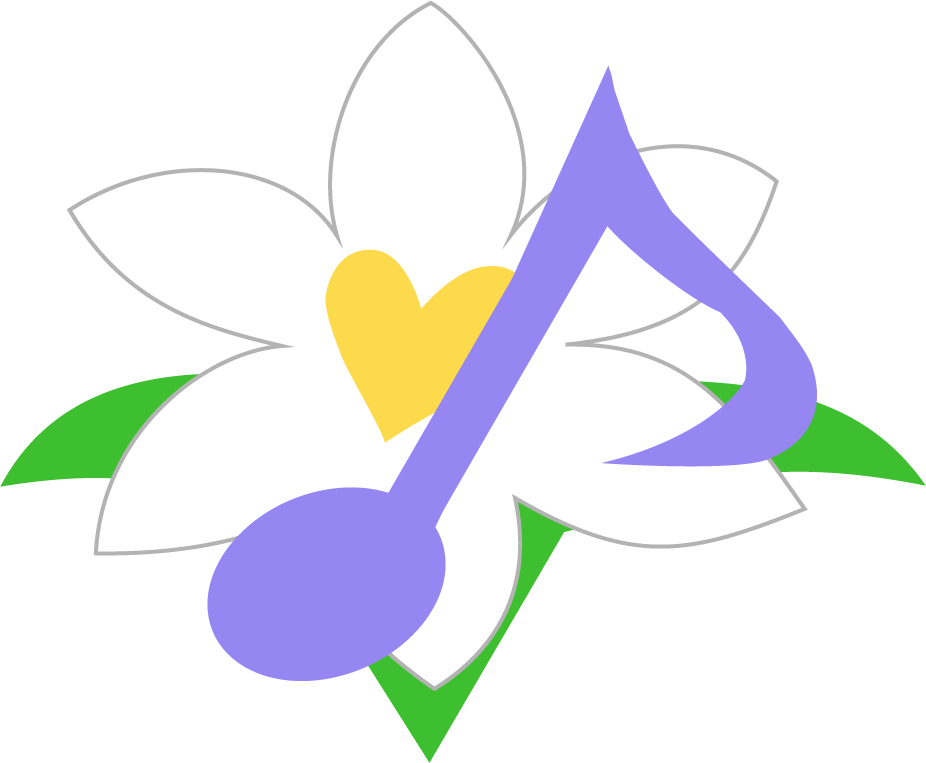n回目のバレンタイン
ー彼女と彼女の愛する人を、私は一生愛し続けるだろう。
彼女が私の友達でなくなってから、一体何年が経つのだろう。
冷めた珈琲を飲みながら、私はボロボロになった昔の手帳を眺める。
大学四年生の時に使っていた手帳には、ポケットにルーズリーフの一部が挟まっていた。
懐かしい。
走り書きの汚い文字。
『お腹空いた』『リゾット食べたい』『私はお肉がいい』などと、交互に違う文字が書かれている。
斜めに曲がった字から思うに、授業中に同じ紙に筆談していたようだ。
所々、英語で書かれているのは、英語開講の授業だったからなのだろう。
何やってたんだか。
愛しいその文字は、紛れもなく彼女の筆跡だった。
*
その年は都内に大雪が降った。翌日が大学入試の試験日だったので、在学生の私達は午後から休講で、サークル活動も禁止だった。
都心ですら積もっているのだから、多摩地域にあるキャンパスは、まるで雪国かと思うほど、真っ白に覆われていた。
当然、寒い。
その寒空の下で、雪遊びに興じる大馬鹿者が、菜瑠とその彼氏、純平だった。
菜瑠は私と同じ大学四年生、純平は二つ年下の二年生だ。
「実璃もおいでよ! 雪だるま作ろう!」
「馬鹿、風邪ひいても知らないよ」
いい歳してそんなことをするつもりはないけれど、雪が降ると少し浮かれてしまうというのはわかる。
出身県は違うけれど、私も菜瑠も滅多に雪が降らない地域から来ているから、積もった状態の雪なんて、ほぼ見たことがないのだ。
「純平!」
「うわ、やめろっ」
菜瑠の投げた雪玉が、純平のコートの襟元に直撃した。ああ、これは服の中に入ったな。
今度は雪合戦が始まったらしい。
純平もやり返そうと雪玉を投げるが、小柄な菜瑠はうまいことそれを避ける。そして純平に走り寄って、両手に抱えた雪玉を今度は近距離でぶつけた。
そして、衝撃を受け流せずに、純平は後ろに倒れた。そして勢いで上に重なる菜瑠。
ああ、もう、完全にアウトだ。
恋人同士のじゃれあいなんか、私もほっておけばいいのだが、そうもいかない。
びしょびしょに濡れた二人の服から雪と泥をはらい、洗濯機に放り込むのは、どうせ私の役目になるのだ。
「はい、そこまで。いい加減、帰るよ」
「「はーい」」
二人は元気に返事をして、ようやく家に向かって歩き出したのだった。
私達三人は、同じシェアハウスに住んでいる。
築二十年のアパートをリノベーションして作られたそこには、個室が10部屋あって、国籍も年齢も性別もバラバラの住人たちが生活している。
シャワールームやトイレやキッチンなど、水回りは共同だ。
ほとんど全員が、同じ国際系の大学に通っている。
広いリビングで一緒にお酒を飲みながら、夜通し人生について語り合ったり、大学の授業のテーマについて議論したりと、充実した毎日を送っている方だと思う。
私達三人は、こんな環境の中にいるが、メンバーの中でも特に壊滅的に英語ができなかった。
もちろん、全ての日本人の中で平均を取ったら、おそらく上位20%以内には入るのだろうが、数多いる留学生や帰国子女たちの中でスラスラとコミュニケーションが取れるレベルではない。
そんな縁もあって、私達三人は、なんとなく一緒にいることが多いのだった。
去年の春に、純平が大学一年生で、シェアハウスに入居し始めた。
そしてそれから一ヶ月も経たないうちに、純平と菜瑠は付き合い始めた。
菜瑠は元々すごくモテる女子だ。高校二年生以降は、彼氏を切らしたことがない。しかし全員と、一年以内に別れている。だから純平とも、あまり長くは保たないだろう。
私はそう思っていた。
菜瑠と私は大学一年生の時からの付き合いで、専攻が同じため、授業もほとんど一緒に出ていた。
中学生や高校生のべったりとも違うけれど、『二人はほんと、いつも一緒だね』と周りから言われる程度には一緒にいたし、その状態に飽きもせず三年間を過ごしていた。
だからある意味、私の方が、菜瑠の彼氏たちよりは、ずっと長持ちしているのだ。
菜瑠はとても飽きっぽい。今まで付き合ったどの彼氏も、菜瑠に『好きな人ができたから』と振られている。菜瑠の容姿は、客観的に見ればものすごく美人というほどではないけれど、学校のクラスで二番目くらいに可愛い女の子で、大概の男の子は、告白されれば簡単に落ちた。そしていつの間にか菜瑠の魅力の虜になり、依存するようになる。
その頃には菜瑠は既に相手に飽きていて、また別の男を好きになる。その繰り返しだった。
まるで酷い女のようだが、そんな菜瑠は、同性である私のことは溺愛してくれていた。
まず三年も離れず一緒にいるし、自分の誕生日もクリスマスも、付き合っている男よりも私を優先して一緒にいた。私が風邪を引けば、授業を休むくらい心配して看病してくれたし、時々凝った料理を作っては、私に振る舞ってくれた。
私の方は別に頼んだ覚えはないのだけれど、そんな風にされれば、そりゃこっちの方にも情が湧く。菜瑠の歴代彼氏と同じかそれ以上に、私は菜瑠を愛していた。
「実璃、今日、焼肉食べに行かない?」
「いいけど……お金、あるの?」
「まあ、なんとかなるって」
「なんともならないと思うけど……」
菜瑠は金遣いも荒い。だけどなんとかなっているのは、彼氏にたくさん貢いでもらっているからだ。純平もバイトをいくつか掛け持ちしてまで、菜瑠に貢いでいる。
純平に、菜瑠のことが好きだと打ち明けられた時は、親友ながら『あの女だけはやめておけ』と忠告した。にも関わらず純平はすっかり堕ちてしまった。もう、どうしようもない。
そして菜瑠は、貢がれた品々の中でいらない物を、時々私に回してくれたりする。
私は断り切れずにそれを受け取り、買取業者のところで換金する。そんなところでよくわからない経済が回っている。
菜瑠もそうだが、私も大概である。いつか売春防止法違反かなんかで逮捕されたりしないか、心配になるくらいだ。
あの雪合戦の後、びしょびしょになった菜瑠と純平は、シャワーを浴びてから二人で部屋に引きこもってしまった。おそらく今頃二人でイチャイチャと盛り上がっていることだろう。
こういう時、私の胸は苦しくなる。別に菜瑠と付き合いたいわけではない。私は彼らのように、自分の人生をめちゃくちゃにされたくはないから。だけど菜瑠が男と寝ているところを想像しただけで私の身体はどうしようもなく熱くなったし、嫌な衝動に駆られた。そこには痛みしかなかった。
「バイト、行ってきます」
「え、こんな雪なのに、大変だね。いってらっしゃい」
純平は真面目だった。菜瑠がどんなに授業をサボって遊ぼうと誘惑したって、やることをやった後はしっかり授業に行っていた。その辺りは、私と少し似ていた。
私も菜瑠がどんなに甘え声で頼んでも、自分の生活ペースを乱すようなことはなかったから。
そして、そのためなのか、菜瑠はいつの間にか、純平のことを本気で愛するようになったらしい。
二月十三日。バレンタインデーの前日だった。
私は菜瑠に頼まれて、純平にあげるためのチョコレート作りを手伝っていた。
「なんで私が……」
「まあ、いいじゃん。後で残りのチョコあげるからさ」
「残りも何も、私が先に味見してるんだけど」
「そっか、そうだった」
菜瑠は馬鹿なんだと思う。
自分がもらった手作りチョコを、実は彼女の友達が作ったんだと知ったら、純平がどんな気持ちになるのかもわからないのだ。だけど、その頼みを断れない私も私だと思う。
シェアハウスの共同キッチンで、純平がバイトに行っている隙をついて、私達はチョコレート味のカップケーキを焼いた。しかし菜瑠がやったのは、卵を割って混ぜるところまで。あとは小麦粉や砂糖の計量も、ついでにボウルに入ってしまった卵の殻の処理も、全部私がやっている。
まあ、ともかくともそれが、私達のバレンタイン作品第一号であった。
純平は大層喜んでくれた。こんな美味しいもの初めて食べた、と言っていた。それは初めて彼女にもらった手作りお菓子だからに決まっていた。私が参照したのは、市販の料理本の中の、ごくありふれたレシピだったからだ。
それから私達は、毎年毎年、一緒にチョコレート菓子を作るハメになった。おそらく純平も、途中から気づいていたと思う。バレンタインデーの前日は毎年、バイトを入れて外に出ていたから。
私と菜瑠が卒業したあとは、三人で別のアパートを借りて、3DKの部屋で共同生活をするようになった。家事の担い手は主に、公務員で九時五時勤務になった私だった。私のお菓子作りのスキルは、年々上がっていった。
何回そうやってバレンタインを過ごしたかわからない。私達は純平に嘘を吐き続けたし、純平は私達の嘘に付き合い続けてくれた。
純平から見たら、私はとても邪魔な存在だったろうに、彼はそんな素振りも全く見せずに、私のこともまるで家族のように扱ってくれた。
しかし、私達の奇妙な共同生活は、急速に幕を閉じた。
その日は奇しくも二月十三日。バレンタインデーの前日だった。
私と菜瑠は七回目のバレンタイン作品を作り上げ、翌日に純平にあげるのを楽しみにしていた。
だけど私は、その時何を作ったのか、どうしても思い出すことができない。
その夜は、純平の帰りが妙に遅かった。二十五歳の純平はその頃、会社員の他に、ピザ屋の配達アルバイトをしていた。
金遣いの荒い菜瑠との家計簿の帳尻を合わせるため、彼は朝な夕な働いて、いつも寝不足だった。
私はそんな純平を心配していたが、菜瑠は、ひとのうちのお財布事情にケチをつけるなとばかりに、私の忠告を無視していた。
翌日の朝まで、純平は帰らなかった。私達は翌日のニュースで知った。
純平はバイクで配達中に居眠りをしてしまったのか、道路のガードレールに自らぶつかり、即死したとのことだった。
菜瑠も私も、純平の親御さんの顔さえ知らず、葬儀の連絡もこなかった。純平は両親とあまり仲がよくなく、自分の交友関係をほとんど話していなかったようだった。
市役所からこの部屋に届いた書類の処理をする時に初めて、役所経由で、親御さんに連絡がついた。荷物の整理や事務手続きなどは、私が全て行った。
菜瑠は、何かをできる状態ではなかった。
ベッドから出ようとしなかった。シャワーすら浴びず、食事も取らずに、ひたすら一人、部屋で泣いていた。私のことも部屋に入れようとしなかった。
菜瑠が食事をとらなくなって二日目の夜、私は無理矢理、菜瑠の部屋に入った。
真っ暗な部屋の中で、その日、私は初めて、菜瑠を抱いた。
私はずるいと思う。今までにないくらい傷ついているだろう菜瑠を、さらに傷つけるかのように、何度も何度も、菜瑠を愛撫した。彼女も何度も声をあげ、私を求めた。
菜瑠の肌は吸い付くようにすべすべで、艶のある声や柔らかな唇を味わいながら、私は、なぜ男たちが彼女から離れられなくなるのか、わかってしまった。
その時から、菜瑠は私の恋人になった。今までと変わらない暮らしのまま、そこに肉体関係だけが新たに加わった。
それから程なくして、菜瑠が妊娠していることがわかった。その子は間違いなく、純平の子だった。
産むな、とは言えなかった。
二十八歳の私達は、市役所に行って、同性パートナー登録をし、私は生まれた子供の養母になった。二〇三〇年の秋のことだった。
*
「みーちゃん、大さじってどれ?」
「ああ、純花。待ってて、今行く」
すっかり大きくなった私達の娘は、今年、初めてのバレンタイン作品を作るらしい。
「あーあー、卵の殻、入っちゃってる」
「だって、難しいんだもん」
「ほんと、しょうがないなあ」
私達は笑う。
なんとかブラウニーを作り上げる。チョコの溶けるいい匂い。
熱々の状態で、ふーふーしながら味見をする。うん、成功。
純平がいなくなってからも、私と菜瑠はバレンタインにお菓子を作り続けた。
何回作り続けたか、何年が経ったのか、もう忘れてしまった。
「そうだ、ママにもあげなきゃね」
純花は小さなお皿にブラウニーを取り分けて、別室に持って行く。
チョコの香りに、嗅ぎ慣れた白檀の香りが混ざる。
「しかし、こんなんじゃ、仁くんに申し訳ないわ。もっと真面目に教えておけばよかった」
「料理は仁がやるからいいの。ねえ、今、何年だと思ってるの? みーちゃんの生まれた平成じゃないんだよ」
「はいはい。でもせめて大さじくらいは使えるようになってね」
全く、いい歳して情けないと思うが、甘やかしすぎてちゃんと教えなかった私も悪い。
「ままー! お腹すいた! けーきまだぁー?」
「はいはい、ケーキじゃなくてブラウニーだよー」
純花が答えると、甲高い叫びをあげて、小さな巨人がバタバタと走り寄ってくる。
エネルギーの有り余る年頃なのだ。
「おばあちゃん!! 一緒に食べよー!!」
「はいはい、ちょっと待っててね」
もう、そんなに早くは動けないんだから。腰も痛いし、膝は去年手術したばっかりなんだから。
歩きながら、写真の中の菜瑠が目に入る。
私と同じくらい皺くちゃの顔をした彼女は、去年の冬に神様の元へ旅立った。
全くどうしようもない。結局あなたは、私の人生をめちゃくちゃにして行ったね。
「もう少しだけ待っててね。まだそっちには行けないから」
私は心の中で手を合わせる。
「おばあーちゃん!! 早く早く!!」
可愛い孫娘は、よく響く声をしている。目元も、あの二人にそっくりだ。
n回目のバレンタインは、良い日になりそうだった。