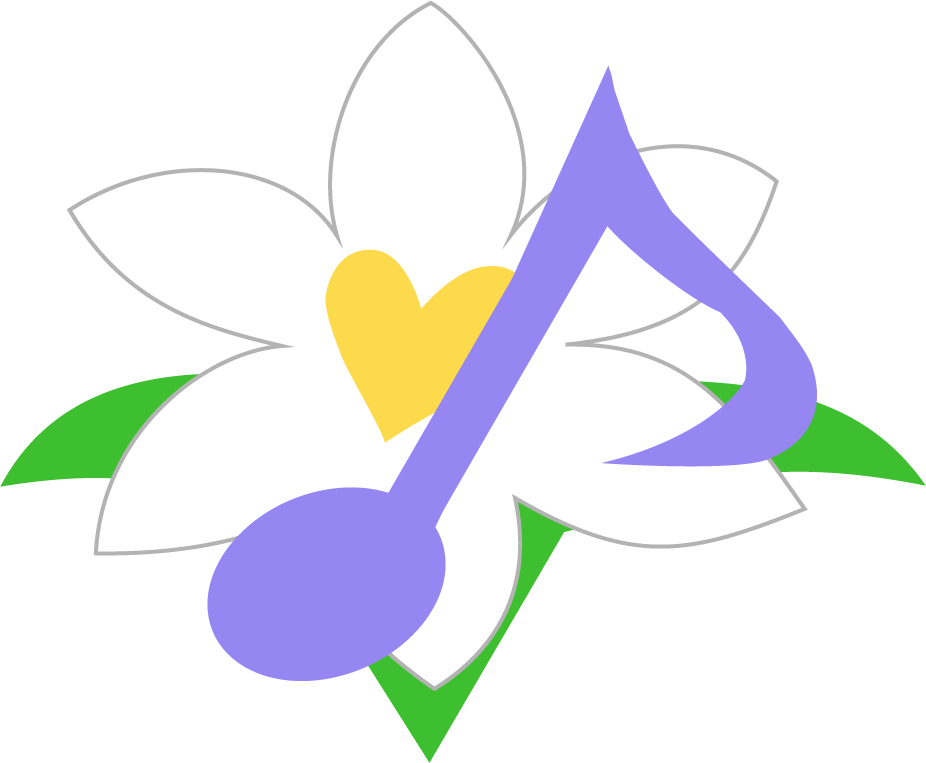風鈴の声
ー友達の女の子と、ひと夏のあやまち。
大学に入学してすぐに、美月は合唱サークルに入ることを決めた。授業の後に練習見学に行くと、そこには、一人の女の子がいた。
「あの、入部したいんですけど」
「え? あ、すみません、私も一年生なんです」
「あ、そうなんだ。先輩方ってまだ来てないのかな」
「なんだか大事な会議があるみたいで。多分もう少ししたら来るんじゃないのかな」
先輩方が来るまでしばらく話していたら、気づいたら打ち解けていて、二人は揃って入部届を出した。彼女の名前は、茉奈、というのだそうだ。
茉奈は中学の時から声楽のレッスンを受けていて、とても澄んだ良く通る美声の持ち主だった。「鈴を鳴らすような声」とはよく言った物だが。茉奈の声はそれに近かった。合唱経験者の美月でも、茉奈の声を聴くと、ただうっとりと聞き惚れてしまうくらいだった。
茉奈と美月は、共に音楽に真剣に向き合い、語り合ううちに、どんどん親密になっていった。音楽の話以外でも、とりとめのない雑談でも、不思議とテンションが合い、一緒にいるといつでも笑いが絶えなかった。
美月は、茉奈と一緒にいると、まるで双子の姉妹がそこにいるような錯覚に陥った。事実、茉奈と美月は性格的にもよく似ていて、周りのメンバーからも、姉妹と評されるほどには、二人一組でいることも多かった。
「美月、お腹空いちゃった。パスタでも食べに行こうよ」
「え、次の二限、授業入ってるでしょ」
「だってお腹空いちゃったんだもん。腹が減っては戦はできぬと言うでしょ」
「……仕方ないなあ」
美月は茉奈を自転車の後ろに乗せて、パスタ屋さんに向かって漕ぎ出した。二限の線形代数の先生、ごめんなさい。私は数学よりパスタを選びます。
茉奈にせがまれると、美月はいつも嫌とは言えない。無理矢理従わされるというのではなくて、茉奈をただ喜ばせてやりたくなってしまう。この気持ちがなんなのかはわからないけれど、それは美月にとって初めてのもので、人知れず大事にしたいものだと感じていた。
しかし、その平和な時間は、そう長くは続かなかった。
それは、ある日の夕方のことだった。春の陽気を飛び越えて、次第に上昇していった気温は、あっという間に大きな雲を作り、突然の雨を地上に降らせた。
傘なんか持ってきていなかったから、茉奈と二人、バス停の屋根の下に潜り込んだ。服はびしゃびしゃになってしまって、先客もおらず、急に下がった気温に身体を震わせながら、二人で身を寄せ合った。
「なんか、急に寒くなってきたね」
「服、びしょ濡れ。嫌になるね」
しかし、待てども暮らせども、雨はやまないし、バスも来ない。よく見るとバスはこの日は運休だった。どうりで、人がいないわけだ。
「仕方ない、家まで歩こう」
真っ黒な雲のせいもあって、辺りはもう暗くなってきており、このままだと身体が冷えていく一方だったので、二人は雨に打たれてびしょ濡れになりながら、大学近くにある美月のアパートの部屋を目指した。
部屋に付くと、二人はすぐに服を全部脱いで、一緒にシャワールームに入った。全身びしょ濡れで、一人が終わるまで待っていたら、もう一人が風邪を引いてしまいそうだったから、一緒に入ることにしたのだ。
「わあ、あったかい」
ユニットバスに少しお湯をためて、無理矢理二人で一緒に湯に浸かった。初めて見る茉奈の肌は、透き通るように白くて美しく、お風呂の熱で上気してうっすら赤く染まり、なんだか見てはいけないものを見てしまったような気がした。
お風呂から上がると、並んでソファーに座り、二人で音楽を聴いた。雨が酷くてもう帰れないと判断した茉奈は、今晩は美月の部屋に泊まることにした。
しかし温まった後に音楽を聴いていると、二人ともなんだかとても眠くなってしまって、夕飯もそこそこに、うつらうつらとしてきてしまった。
そのまま眠りに落ちて、しばらく時間が経った頃、美月は自分の身体に小さなくすぐったいような疼きを感じて、目を覚ました。
気づいたら、美月の服は乱れて、胸部が露わになっており、その上に顔を近づけて舌を伸ばす、茉奈の姿がそこにはあった。
あまりの衝撃に、美月は一瞬言葉が出なかった。けれど、とても熱く甘美な生まれて初めての感覚に、気づけばどうしようもなく、ただ声を上げていた。
「茉奈、なに、してんの」
「見ればわかるでしょ。味見」
「何考えてるの」
「美月の身体、綺麗だなって」
「そういうことじゃない」
だけど、反論しながらも、強く抵抗することは美月にはできなかった。
「美月だって、ずっと私にこうしてほしかったんでしょ。バレバレだよ」
「そんな……」
でも、そうなのだ。その行為は多分、美月が無意識に茉奈に対して求めてしまっていたものなのだ。このとき美月には、それが唐突にわかってしまっていた。
「……やっぱり、美味しい」
茉奈の行為はどんどんエスカレートしていき、舌や指が、美月の身体のあちこちに這わされていった。
「……馬鹿」
身体の輪郭を撫で回された挙げ句、奥にまで侵入されて、美月の息は絶え絶えになり、ついに頭が真っ白になってしまった。
「ほんとに、なに、やってるの」
「気持ちよかったくせに。……ねぇ、私にも、して?」
茉奈は妖しげに笑って、自身の服をはだけさせる。白い柔らかそうな肌が露わになる。それを見ると、美月はたまらなくなって、茉奈に吸い付くように覆い被さった。そして、先ほど茉奈が美月にしたように、全身に唇を這わせ、茉奈の敏感な場所を弄ぶ。
「美月っ……」
「……茉奈、可愛い」
茉奈が甘い声を上げる度に、美月は胸の奥がきゅっとなるのを感じて、触れる手を止めることができなくなった。
「美月、もう駄目……」
「自分が、先に仕掛けたくせに」
茉奈の甘い声も、吸い付くような白い肌も、とろんとした表情も、全てが美月を狂わせた。茉奈が「止めて」というのも聞かずに、彼女をただ責め続けた。茉奈の身体は何度も何度も弾け、荒くなった二人の息で、部屋の窓は曇っていた。
それからは、茉奈は度々美月の家に入り浸るようになった。ただでさえ、授業をサボりがちな二人は、時には丸一日、何もせずに、布団の上で抱き合っていることさえあった。
茉奈と触れ合う度に、美月は自分の心身のコントロールが外れていくのを感じた。茉奈の全てが欲しくて仕方なかった。けれど、どんなに口付けをしても、全身を愛撫していても、茉奈の心が自分のところにはないことを、美月は気づいてしまっていた。
しかし、会う度に身体の触れ合いを求めてくる茉奈を拒めるはずもなく、その度に上気した肌や、美しすぎるその声に絡め取られるようにして、美月の心は、深い深い沼の底に沈んでいった。
「美月……話があるの」
崩壊の日は、ある日突然、やってきた。
茉奈には、もともと付き合っている男性がいるのだという。その人は留学中で、ずっと遠距離恋愛をしていたのだが、来月、帰国するのだという。そしてそれは、茉奈がこの部屋を出て行き、この関係も終わりになるということを意味していた。
茉奈は泣きながらその話をしたが、美月は茉奈を許すことはどうしてもできなかった。茉奈は、美月を利用したのだ。留学中の彼氏に会えない寂しさを紛らわすために、美月と身体的関係をもった。ただそれだけだったのだ。
どうしても許せないのに、どうしてそうなったのかはわからないけれど、茉奈が部屋を出て行くその日、二人はこれまでの中で一番、濃密に身体を重ねた。何度も声を上げた。その度に美月の目からは涙がこぼれた。それは、茉奈も同様だった。
ひとのことを利用して傷つけておいて、どうしてそんな風に涙を流せるのだろう。美月はせめてもの最後の抵抗に、茉奈の全身に紅い跡を付けてまわった。茉奈のことが憎らしくてたまらなかった。
風が吹いて、外に吊してあった風鈴が揺れて音を鳴らした。夏の終わりを告げるかのようなその音は、透き通るようなのにやけに艶やかで、茉奈の声に似ていた。